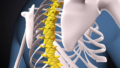整体の現場で「関節がズレていますね」と伝えることはよくあると思います。
しかし、その“ズレ”が具体的にどうして痛みにつながるのかを、理論的・生理学的に説明することは意外と難しいものです。
今回は、関節のズレによって起こる痛みのメカニズムを、最新の研究や生理学的知見をもとに整体師の視点で深堀りしていきます。

■ 「関節がズレる」とは何か?
整形外科的な意味でのズレは「脱臼」「亜脱臼」といった明確な骨の逸脱を指しますが、整体師が使う“ズレ”はそこまで強い変位を意味しないことが多く、以下のような状態を含みます。
- 骨の微細な変位(位置異常、回旋、傾き)
- 関節周囲の筋・靭帯のアンバランス
- 筋膜の引きつれや癒着による関節可動の不一致
- 神経系の再統合のズレ(感覚と動きのミスマッチ)
一見小さなズレでも、痛みや機能障害を引き起こす可能性があるため、構造的な変化以上に“感覚”や“神経”の要素も含めて理解していく必要があります。
■ 関節のズレが痛みを生む3つの主なメカニズム
① 関節受容器の異常興奮
関節を包む関節包や靭帯にはメカノレセプターと呼ばれる固有受容器が豊富に分布しており、身体の位置情報や張力を感知しています。これらの受容器は骨の位置や関節の緊張状態に敏感で、ズレが生じると異常な刺激を脳に送り続けることになります。
研究によれば、こうした異常入力は中枢神経系での痛み感受性(セントラルセンシタイゼーション)を高める要因となるとされています(Lephart & Riemann, 2002)。
🧠 参考論文
Lephart SM, Riemann BL. The role of proprioception in the management and rehabilitation of athletic injuries. Am J Sports Med. 2002.
② 筋・筋膜のアンバランスと虚血性疼痛
関節がズレることで関節周囲筋や筋膜のバランスも乱れ、ある筋は過緊張、別の筋は抑制されるような状態になります。これにより**血流障害(虚血)**が起き、発痛物質(ブラジキニン、ヒスタミン、プロスタグランジンなど)の蓄積により慢性的な痛みが発生します。
特にトリガーポイント理論に基づけば、ズレによる姿勢・運動の偏りは活動性のある筋膜痛の背景として臨床でもよく見られます。
③ 感覚運動不一致による長期的な痛み
近年注目されているのが、感覚と運動のミスマッチによる痛みの発生です。
自分が「こう動いている」と思っている身体感覚と、実際の身体の動きがズレていると、脳は“違和感”として痛みを発生させることがあります。
これは脳の体性感覚野や運動野の可塑的変化(マッピングの乱れ)が原因とされており、慢性疼痛患者ではよく確認されています(Hodges et al., 2013)。
■ 整体師ができる臨床的アプローチ

● 関節のアライメント調整
関節モビライゼーションや軟部組織への徒手アプローチを通じて、関節の生理的な動き・配置を取り戻すことは、受容器の正常化に非常に効果的です。
微細なズレの感覚を持つ施術者ほど、関節の「滑り」「遊び」「引っかかり」などに敏感に対応できます。
● 筋・筋膜の再教育
過緊張している筋をリリースするだけでなく、サボっている筋(抑制されている筋)に再び仕事をさせることが大切です。
- 例:腸腰筋が抑制→腰方形筋や脊柱起立筋が代償して腰痛
- 例:多裂筋の不活性→仙腸関節のズレと関連
こうした部位は、姿勢保持筋・インナーマッスルとしての役割が強く、関節の安定性に直結します。
● 神経系からのリセット
視覚・聴覚・触覚など多感覚の入力を使って、ズレた身体イメージを修正する神経リハビリ的アプローチも重要です。
- 鏡療法
- バランスディスクでのコーディネーショントレーニング
- PRI、DNS、フェルデンクライスなどの感覚再構築アプローチ
これらを施術後の再教育として取り入れることで、「戻った関節」が元に戻りにくくなります。
■ 日常生活に潜む“ズレ”の原因と予防

実際、関節のズレの多くは、日常の「クセ」が原因となります。
- 椅子に座ると必ず脚を組む
- デスク作業で常に片側に体重をかける
- 同じ方向ばかりを見ながら作業している(例:右モニターのみ使用)
こうした生活パターンを修正しない限り、いくら整体で整えても再発します。整体師としては、施術後のセルフケア提案と生活指導までを含めて初めて本当の“治療”になるでしょう。
■ 最後に|“ズレ”を感覚・構造・神経で見る整体へ

関節のズレと痛みは、単に骨の構造的な問題だけではなく、感覚情報の誤認や脳内処理、筋膜の張力異常などが複合的に絡み合って生じています。
整体師がこの視点を持つことで、目の前のクライアントに対する評価・施術・指導がより精度高くなり、慢性痛への理解と対応力が一段と深まります。
そして、どの地域であっても、施術者が“ズレの意味”を論理的に語れることが、信頼される治療家への第一歩になるはずです。